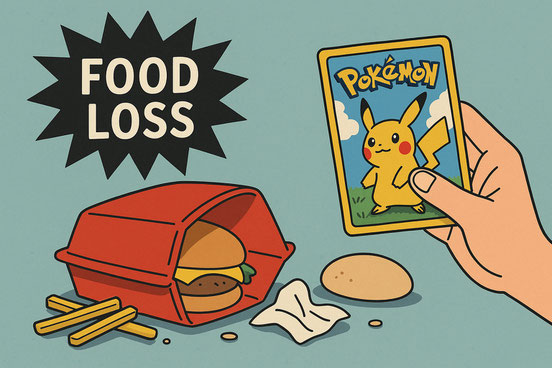マクドナルドのポケカ転売のフードロス問題
マクドナルドが販売した「ポケモンカード」をめぐり、転売や混乱が話題となっていますが、今回着目したのは「カードだけ欲しくて、ハッピーセットを大量購入した挙句に食べ物を大量に捨てた人がいた」 という問題です。
この現象は、単なる一消費者の行動にとどまらず、フードロス問題・消費者倫理・企業の社会的責任にまで広がるテーマだと考えられます。
フードロスは「社会全体の損失」
農林水産省によれば、日本のフードロス量は年間約523万トン(令和4年度推計)にのぼります。
家庭から出る食品ロスだけでなく、外食・小売など事業活動に伴うロスも深刻です。
今回の件では、本来「食べ物を提供する」ことを目的とする販売で、大量に廃棄が出てしまったという点が大きな問題です。
-
食べ物を粗末に扱うことは倫理的にも批判を免れません。
-
加えて、廃棄処理にもコストがかかり、環境負荷を高める結果となります。
消費者保護法制との関わり
法律上「食べ物を捨てること」を直接的に禁止する規定はありません。
しかし、関連する法制度は存在します。
-
食品リサイクル法:事業者には食品廃棄物の削減・リサイクル義務が課されています。
-
消費者教育推進法:持続可能な社会を目指す観点から、消費者の適切な行動を促すものです。
つまり、今回のような行為は「法的制裁対象」ではないにせよ、国が問題視している消費行動そのものにあたると言えます。
企業側の責任と工夫
マクドナルドの立場からすれば、「カードが主目的になって食べ物が無駄になる」という事態は本意ではないでしょう。
しかし、景品と食品をセットで販売する以上、企業には次のような配慮が必要です。
-
販売方法の工夫
例:カードを単体販売する、あるいは食べ物の寄付と連動させる。 -
消費者への啓発
「食べ物を大切にしてください」といったメッセージを併せて発信する。 -
CSR(企業の社会的責任)対応
余剰食品が出た場合には、フードバンクなどへ寄付する仕組みを強化する。
倫理と法の狭間
今回の事例は「法律に違反しているわけではないが、社会的には強く非難される行為」の典型例です。
弁護士の視点から言えば、こうしたケースでは 「法的リスク」よりも「社会的信用の毀損リスク」 の方が大きいと感じます。
SNS時代においては、一部の消費者の行動が企業イメージ全体に影響を及ぼします。
したがって、企業は販売戦略を立てる際、法律遵守だけでなく 社会的影響まで考えたリスクマネジメント が欠かせません。
まとめ
マクドナルドのポケカ騒動は、転売や炎上の問題にとどまらず、食べ物を粗末にするフードロスの問題を浮き彫りにしました。
-
消費者には「買った食べ物を無駄にしない」倫理観が求められます。
-
企業には「景品と食品をどう扱うか」という社会的責任が課されています。
今回の騒動をきっかけに、私たち一人ひとりが「消費行動の意味」を考えるきっかけとなるのではないでしょうか。