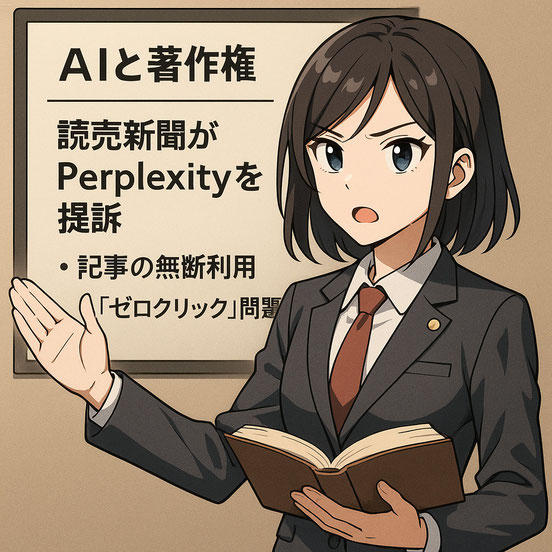1. 事件の概要
2025年8月7日、読売新聞グループ本社と東京・大阪・福岡の各本社が、米AI企業「Perplexity」を著作権侵害で東京地裁に提訴しました。
請求の中身は、記事約11万9千件と画像の無断利用に基づく使用差し止めと、約21億6,800万円の損害賠償。
問題視されているのは、Perplexityが提供する生成AIが、記事を要約・提示することで、ユーザーが元記事を読みに行かずに完結してしまう「ゼロクリック検索」の構造です。
2. 法律的な争点
今回の事案で主に議論されるポイントは以下の通りです。
-
複製権の侵害
著作権法21条が定める「著作物を複製する権利」に該当するか。AIが記事を学習・要約する過程で、原文を再現または実質的に利用している場合、複製権侵害の可能性があります。 -
公衆送信権の侵害
著作権法23条により、著作物をインターネット等で送信する権利が保護されています。AIが要約や記事全文をユーザーに配信する行為が、この権利の侵害に当たるかが焦点です。 -
学習利用の特例との関係
日本の著作権法は2018年改正で、AI開発等のための情報解析利用を一定条件下で自由化しました(著作権法30条の4)。
ただし、これは「著作権者の利益を不当に害しない」ことが前提で、配信や利用者への提供は対象外です。
今回の争いでは、この特例の範囲をどう解釈するかが重要になります。
3. ビジネスモデルと「ゼロクリック」の問題
従来、検索エンジンは記事タイトルや短い抜粋を表示し、ユーザーを元サイトへ誘導していました。
しかし生成AIは、質問に対し記事内容をまとめて提示するため、ユーザーが新聞社サイトへアクセスする必要がなくなります。
結果として、新聞社の広告収入や購読契約への誘導機会が失われる可能性があります。
この「ゼロクリック」は法的には直接損害を立証しづらい一方、ビジネス的には重大な影響を与え得ます。
4. 海外の動向
-
米国では、News Corp(Wall Street Journal運営)などがPerplexityを含むAI企業を提訴中。
-
欧州でも、AI企業に対し、著作物利用契約の締結やライセンス料支払いを求める事例が増えています。
-
多くの国で「学習利用」と「利用者への提供」の線引きが争われています。
5. 実務的示唆
この訴訟は、報道機関だけでなく、企業や個人が運営するブログ・ウェブサイトにも影響し得ます。
特に以下のような対応を検討する価値があります。
-
契約条項の整備:コンテンツ利用に関する禁止事項や利用料の明確化
-
技術的対策:robots.txtやメタタグによるクローリング制御
-
著作権表示の徹底:AIが判別しやすい形式での著作権明示
-
ライセンス交渉:AI企業との間で利用契約を結ぶ枠組みの検討
6. まとめ
今回の訴訟は、日本初の大規模「AI vs メディア」の著作権侵害裁判として注目されます。
判決の行方次第で、生成AIの利用方法やビジネスモデルが大きく変わる可能性があります。
法律実務の現場でも、今後ますます「AIと著作権の境界線」を巡る相談が増えていくでしょう。