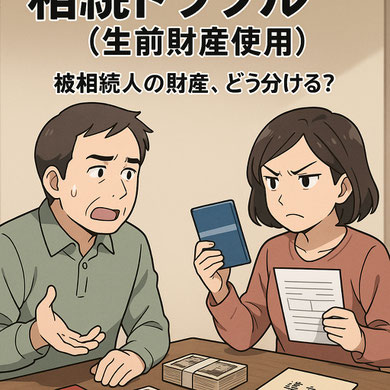こんにちは。弁護士の山口統平です。
今回は、「被相続人(亡くなった方)の財産を生前に使っていた相続人が、他の相続人から使った分の請求を受けた」というケースについて、解説していきます。
実際によく相談を受けるテーマであり、相続トラブルの典型例の一つでもあります。
1.生前の財産使用は「問題になる」のか?
親の生前、生活費や介護費用を援助していたり、逆に親の預金を自由に引き出して使っていたりする相続人がいることは、決して珍しくありません。
しかし、相続開始後、他の相続人から
-
「どれだけ使ったのか説明してほしい」
-
「使った分を戻してほしい」
と請求される場合があります。
この場合、問題となるのは、
-
正当な理由があったか
-
被相続人本人の同意があったか
-
使った金額や内容が妥当だったか
です。
単に「親が生きていたから問題ないだろう」と考えていると、後に大きなトラブルに発展することがあります。
2.法律上はどう整理される?
民法上、相続人は被相続人の権利義務を引き継ぎます(民法896条)。
したがって、生前に不当に財産を減らした場合、他の相続人は
-
不当利得返還請求
-
損害賠償請求
といった法的手段をとることができます。
また、特別受益(民法903条)という考え方も関係してきます。
もし生前に特別な利益(高額な援助など)を受けていた場合には、相続分を計算する際に「すでに受け取った」とみなして調整されることがあります。
3.どんな場合に返還義務が発生する?
次のような場合には、返還や説明の義務が発生する可能性が高いです。
-
被相続人の明確な同意がなかった
-
生活費とはいえない目的(私的な浪費など)で使用していた
-
金額が不相当に大きい
-
帳簿や領収書などの裏付けがない
反対に、たとえば
-
被相続人の介護や生活維持のために使った
-
領収書や記録がきちんと残っている
-
被相続人の口頭や書面による同意があった
場合には、正当性が認められることもあります。
4.トラブルを防ぐためには
生前から以下を心がけておくことが重要です。
-
使ったお金の記録(メモやレシート)を残す
-
できれば家族全体で情報共有する
-
委任契約書や同意書を作成しておく
-
大きな支出は事前に相談する
「親だから自由に使っていい」という感覚は、法律上は通用しないこともあります。
後から「盗った」「ズルい」と揉めないよう、慎重な管理が求められます。
5.まとめ
被相続人の財産を生前に使っていた場合、
「親が生きていた間だから問題ない」と軽く考えるのは危険です。
相続開始後、他の相続人から請求されるリスクがあり、
場合によっては、使った金額の返還や、相続分の減額を求められることもあります。
もしこのような状況に心当たりがある場合、
また逆に、他の相続人の使い込みに疑問がある場合は、
早めに弁護士に相談することをおすすめします。
専門家の介入によって、冷静かつ円満な解決への道筋をつけることができます。
山口統平法律事務では、こういった相続案件も多く取り扱っております。
ご依頼につきご不明点がございましたら、初回30分は無料で弁護士が法律相談に応じます。
まずはお気軽にお問い合わせください。